文=菅野浩二(ナウヒア) 写真=本人提供、小黒冴夏
柳田宙輝(やなぎだ・ひろき)さん|株式会社あいづのあいつ 代表取締役
東京都出身。N高等学校を卒業後、2025年3月に武蔵野大学のアントレプレナーシップ学部を卒業。在学中の2024年10月に株式会社あいづのあいつを設立し、おむすび屋「結(むすび)」の運営を手がけている。社名はコピーライターとして活躍し、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部で教壇に立つ梅田悟司先生に命名いただいたという。趣味の一つはコーヒーを入れることで、豆を挽くところからこだわっている。「現代人は忙しく、コーヒーも入れようと思えばすぐに入れられますが、そういうものに時間をかける心のゆとりを大切にしたいと思っています」
挑戦意欲がある同級生のほうが今後の人生にとって財産になる
中学校も高校も進学校を受験して合格した。けれども、進学校での生活はどうにも肌に合わなかった。柳田宙輝さんは「シンプルに言うと、おもしろくなかったんです」とあけすけに話す。
武蔵野大学在学中の2024年10月に株式会社あいづのあいつを設立
国立大学の附属高校から離れる決意をしたのは、「このまま偏差値の高い大学に入ったとして、おもしろいのかな」と自問した際に「おもしろくないだろうな」という答えが出てきたからだ。高校3年生のときに通信制のN高等学校に転入学をした。
これまでの反省を生かし、大学受験では偏差値で学校を選ぶのはやめようと考えていたとき、当時通っていた塾の塾長に「柳田君が高校を卒業するタイミングでこういう学部ができるんだけど」とパンフレットを見せてもらった。武蔵野大学が日本で初めてアントレプレナーシップ学部を開設することを知り、俄然興味が湧いた。「高い志と倫理観を持ち、失敗を恐れずに挑戦し、新たな価値を見出し、創造していく」という文言は壮大すぎると感じたが、だからこそそこで学ぶ価値があるのでは、と感じたという。
「『そういう文章に誘われて入学してくる人たちはどこか変わり者で、やっぱりおもしろいんだろうな』と思ったんです。全く新しい環境に飛び込んでくることができる勇気のある人たちは限られていますよね? つまり、どこか常識はずれで、僕も大いに刺激を受けるだろうと考えました。1期生ですし、頭がよいまじめな同級生より、挑戦意欲があって頭が柔らかい同級生のほうが今後の人生にとって財産になるなと思い、武蔵野大学のアントレプレナーシップ学部に入学することに決めました」
スタートアップスタジオ「Musashino Valley」に拠点に働く
1年次の授業で印象に残っている時間の一つが、柏谷泰行先生のプロジェクトの授業だ。「自分の周りの人を幸せにしてきてください」というテーマが出され、「自分は誰を幸せにしたいのか」「どうして幸せにしたいのか」「どういう方法で幸せにしたいのか」と自問自答を繰り返した。
熟考の末、離れて暮らし、しばらく疎遠になっていた母親と会うことに決めた。自分から連絡して一緒に食事を楽しみ、花束を渡して「いつもありがとう」と伝えた日は忘れられない。母親の笑顔を見て、「誰かを幸せにする」という行為がビジネスの本質であるばかりでなく、自分の生き方の原動力になることを知った。
「おもしろいか、おもしろくないか」という判断基準で動いていく
3年次にインターンシップを経験した仲間たちと。柳田さんは左から2人目
武蔵野大学のアントレプレナーシップ学部に入ってからも、「おもしろいか、おもしろくないか」という判断基準は変わらなかった。柳田さんは振り返る。
「入学してすぐの1、2学期に受けた授業の中では、論理性と実践性にユーモアがほどよく交ざり合った寺田知太先生の授業が一番おもしろかったんです。寺田先生はインクルージョン・ジャパン株式会社という投資会社の取締役を務めているんですが、直談判して『一緒に働きたいんです』と伝えました。1年生の夏でしたね。『おもしろそうだからとりあえず行ってみる』と本能のままスタートしたんですが、それが“インターンシップ”というかたちでした」
その後も「おもしろそう」という本能に突き動かされながら、人生経験を積んでいく。
外部講師として講義にきた『Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)』の副編集長から「インターンを募集しています」と伝えられたときは、友人に誘われてオフィスを訪問。1年次の冬に、メンズファッション誌『オーシャンズ』のウェブメディアを運営するOCEANS Web編集部でインターンシップをすることになった。
2年次には入学式ですぐに仲良くなった森輝(ひかる)君とともに、「青春18きっぷ」を利用して東京から北海道までを縦断した。2年次が終わる2月にはベトナム、タイ、カンボジア、マレーシアの4カ国を旅している。同じ学部の津吹達也先生のゼミで「カンボジアを訪れて現地で商品開発をして現地で販売する」というプロジェクトを実施しており、友人の一人から「カンボジアに1カ月いるから遊びにきてよ」と誘われたのがきっかけだった。どちらも「貧乏旅行」だった二つの旅行を通して、生きるたくましさも身についた。
3年次の初夏には、寺田先生からの誘いに飛びついた。寺田先生に「大学の近くでビルを売ろうとしている知り合いがいるから、そのビルを改修してシェアハウスを学生向けに運営したらおもしろくないか」と声をかけられ、迷うことなくプロジェクトに参画する。柳田さんは明かす。
「アントレプレナーシップ学部は1年生が寮制で、しかも1期生の僕たちにとって寮生活は特別に濃い思い出として刻まれています。同期のためにもう一度コミュニティーをつくり、さらに後輩たちへと連鎖していく場として機能させられるのでは、という点に大きなおもしろみを感じました。6階建ての建物だったんですが、そこの設計や間取りを見ていろいろ考えているなかで、1階はうちの学部らしく何かに挑戦できるスペースにしたいと思いました。そこで、今一緒に株式会社あいづのあいつを運営している山口奈々さんが『おむすび屋を開いてみない?』と提案してきて、そのアイデアがとても魅力的に感じました」
3年次の9月におむすび屋「結(むすび)」をスタートさせる
日本橋にあるバー「THE FLYING PENGUINS(ザ・フライングペンギンズ)」などで週1回の営業を中心に活動する。中央は事業パートナーの山口奈々さん
残念ながらシェアハウスを運営する計画は頓挫する。大手企業が自分たちより高い値段を提示したからだ。けれども、おむすび屋の夢は捨てられなかった。実際、自分たちは福島県の西会津町で米をつくっていた。柳田さんは説明する。
「そもそも、大学1年生の12月に西会津町の新米試食会が東京の日本橋で開かれていて、そのイベントに行く機会がありました。そこで西会津町との最初の出合いがあって、次の年の5月に田植えに行ったんです。そこから西会津に通い始め、社会共創型コミュニティーである社会創発塾などと一緒に米づくりをするようになりました。西会津のお米の魅力を東京で発信できる点、人と直接対面して“有形”の商品を手渡せる点、日本文化そのものを事業の軸にできる点におもしろさを感じて、本格的におむすび屋を開きたいと思うようになりました」
福島県西会津町の魅力を広め、持続可能な地域づくりをめざすなかで、3年次の9月におむすび屋「結(むすび)」をスタートさせた
福島県西会津町の魅力を広め、持続可能な地域づくりをめざすなかで、3年次の9月におむすび屋「結(むすび)」をスタートさせる。その取り組みがそのまま卒業プロジェクトになった。3年次の出来事で特に記憶に残っているのは、おむすび屋を始めたとき、最初に出店した場所にゼミ生の全員に来てもらって、そこでゼミを行った経験だ。実際に自分たちがむすんだおむすびを食べてもらいながら、さまざまなフィードバックを受けたという。
その後、人と人とのつながりで紹介してもらった日本橋にあるバー「THE FLYING PENGUINS(ザ・フライングペンギンズ)」などで週1回の営業を中心に活動しながら、メンバーたちと「何のためにやってるんだっけ?」という根本的な話を頻繁にして、おむすびをむすび続けていく。立ち上げからちょうど1年がたったとき、「やるしかない」という決意を固めて、2024年10月22日に株式会社あいづのあいつを登記した。
大学4年次のうちの学生起業は、「やっぱりおもしろいんだろうな」と思って入学した武蔵野大学アントレプレナーシップ学部での集大成となった。卒業直前の2025年2月に開催された「EMC GLOBAL SUMMIT」で、おむすび屋「結」のプレゼンテーションは最後に設定された。武蔵野大学のアントレプレナーシップ学部生のほか、起業をめざす都内の学生やアジア各国の大学生が登壇するコンテストに際して、「最後の最後、1期生である僕たちが賞を取らないわけにはいかない」と意気込んで熱っぽく話すと、「EMCオーディエンス賞」と「起業時代賞」を受賞。最後の最後のダブル受賞は大きな自信となった。
「おむすび屋『結』をやっていておもしろいと感じるのは、人と人のつながりがどんどん広がっていく瞬間です」と話す柳田さんは、今も「自分の周りの人を幸せにしてきてください」というテーマを追っている気がしている。
「やりがいの一つは、第二のふるさとである西会津に帰ったときに『ありがとう』と言ってもらえること。その言葉は何よりうれしいですし、自分としては、誰かの幸せのためにおむすびをむすんでいるんだなという感覚があります」
「おむすび屋『結』をやっていておもしいと感じるのは、人と人のつながりがどんどん広がっていく瞬間です」
※記事中の肩書きは取材当時のものです。また、学校名は卒業当時の名称です。
関連リンク
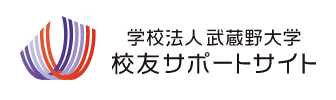













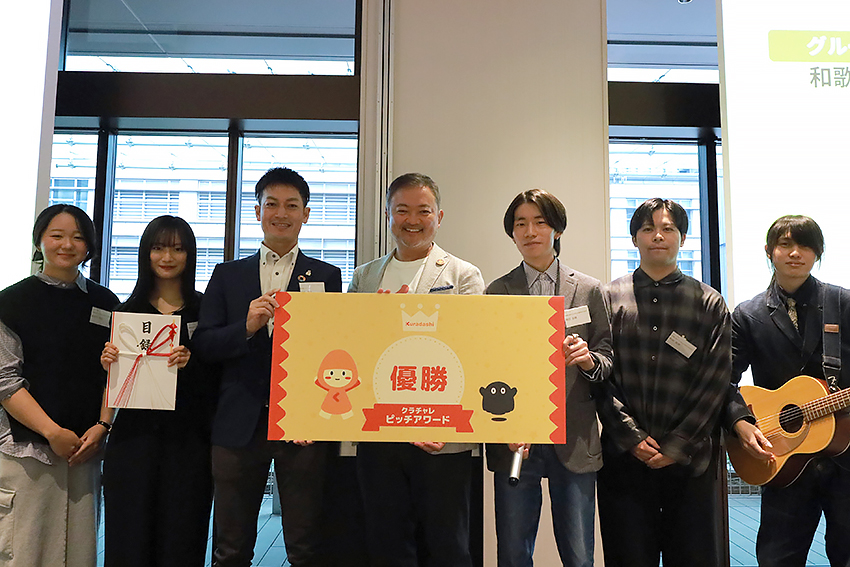



コメントをもっと見る