文=菅野浩二(ナウヒア) 写真=本人提供、鷹羽康博
深澤佳歩(ふかさわ・かほ)さん|株式会社ヘラルボニー
東京都出身。東京都立東大和南高等学校を卒業後、2020年3月に武蔵野大学人間科学部の社会福祉学科を卒業。在学中に国家試験に合格し、社会福祉士の資格を取得した。2020年4月から株式会社ヘラルボニーに勤務する。入社1年目にして、岩手県盛岡市の川徳百貨店(パルクアベニュー・カワトク)にオープンしたブランド初の常設店の店長を務めた。得意なスポーツはバスケットボールで、高校にはスポーツ推薦で入学し、キャプテンと司令塔として活躍した。
障害のある人たちと過ごし、子ども心に自らの固定観念に違和感を感じる
まだ小学4年生の少女は、その時間が進路や仕事につながるとは夢にも思っていなかっただろう。およそ20年前の冬、身体障害のある人たちが全国から集まるスキーキャンプに参加した。深澤佳歩さんは鮮やかに思い出す。
小学4年生のころの経験が現在の仕事につながっている
「長野県で1週間ほど行われたスキーキャンプだったんですが、幼なじみのお兄さんが身体に障害があって、そのご家族に誘われたんです。同じ部屋に大学生1人、高校生2人、中学生1人、小学生3人で寝泊まりして、私と幼なじみ以外はみんな身体に障害がありました。なかでも一つ年下の女の子と仲良くなって、さまざまな障壁とぶつかりながらも、自分自身、そして社会と向き合っている姿に感じるものがありました」
ボランティアとして参加したスキーキャンプでは、子ども心に自らの固定観念に違和感を感じたという。ある日の夜ご飯はバイキング形式だった。お盆に皿を並べて、トングで食事を取らなければならない。新しい友人は手の形が自分たちとは少し違うから、大変だろうな、助けてあげようと思った。
「私が取ってあげるから好きなもの言って」と伝えると、「ここにお盆を置いてもらうだけでいいよ」と曲げた腕を差し出された。その子は置かれたお盆の上に器用にバランスよく好きな食べ物を盛りつけていった。そのとき、「なんで私はこの子のことを助ける対象として見たんだろう」と、自分の考え方に引っかかりを感じた。
「武蔵野大学を選んだのは現場実習が充実していると思ったからです」
その決まりの悪さはずっと心のなかに残っていた。高校3年生のとき、進路について悩んでいると、自然とあの冬の出来事が思い出された。本当は「助ける」という考えじゃいけないんじゃないか──中学生のときに授業で車いすバスケットボールを体験した時間も印象深く、福祉の道に進みたいと考え、福祉関係に強い大学を探した。深澤さんは明かす。
「あの冬の経験を経て、入学当時は『障害のある人たちを助けたい』というより『寄り添いたい』という思いのほうが強かったと思います。障害のある人たちが自分の人生を生きていくのに横並びで歩いていくイメージですね。武蔵野大学を選んだのは現場実習が充実していると思ったからです。自己推薦型の選抜制度である『ムサシノスカラシップ選抜』 の制度を利用して、合格をいただくことができました」
「なんでそうなったんだろうね」という問いに頭を絞る日々
現在も定期的に友人たちと集まり、渡辺裕一先生(右から2人目)を囲む。深澤さんは右から3人目
武蔵野大学での学びは掛け値なしに濃厚だった。
社会福祉学科で教授を務める、尊敬する渡辺裕一先生が「なんでそうなったんだろうね」と問いかけるたびに、頭を絞りに絞った。たとえば子どもを虐待している親がいたとして、社会的には虐待する親が悪いと認識される。
けれども、裕一先生は安易な思考停止を許さなかった。「その親が虐待してしまう理由はなんなんだろう?なんでそうなったんだろうね」といった問いを発し続けた。虐待する側にも、障害のある人と距離を置く側にも、それなりの理由があるかもしれない。裕一先生の「なんでそうなったんだろうね」という口癖は、福祉に根本から向き合う姿勢を育んでくれた。
3年次に裕一先生の実習クラスを選択すると、将来、福祉にどう関わるのかといった迷いは徐々に晴れていった。深澤さんは振り返る。
「武蔵野大学に入学してから、障害の分野に行くか、高齢の分野に行くか、医療系に行くか、私のなかではずっと揺れていました。ただ、裕一先生の授業を受けているうちに、どの分野に進むべきなのかではなく、『差別』や『障壁』の根本的な問題について考えることが増えていって、その原因を解決していくような道に進みたいなと思うようになりました」
同時に「まだ迷いがあるなら福祉の世界を幅広く見られるほうがいいのでは?」という裕一先生のアドバイスに従い、実習先には地域包括支援センターを選択する。約2カ月、週に4回、支援や介護が必要な人と接するなかで、福祉の現場の厳しさも目の当たりにした。人手不足をはじめとする問題を体感し、「なんでそうなったんだろう」と考えざるを得なかった。
裕一先生の教えどおり福祉の根本に立ち返ると、おのずと自分なりの答えが見えてきた。深澤さんは言う。
「少しでもいいから、福祉の根底を変えられないかなと思ったんです。今の社会にいろいろな障壁が多すぎて『自分らしくあること』を諦めている、諦めざるを得ない人がたくさんいると思います。もっとその人らしさを尊重できる社会をつくりたいなあと。それを阻んでいる原因の一つは『わからないこと』だと考えました。たとえば認知症や障害のある人に対する知識がなく、接し方もわからないから距離をとってしまう。福祉を受ける人たちへの知識や関わり自体がもっと身近なものになれば、誰もが生きやすくなるのではと思いました」
知的障害のある作家たちとのプロジェクトに心引かれる
深澤さんが働くヘラルボニーは、作家が描いたアート作品を軸にさまざまなプロダクトを制作している
2019年、大学4年生になったばかりのある日、どうやったらもっとみんなが自分らしくいることができるのかと考えていると、ふとある発信を思い出した。確か、知的障害のある人たちが描くアート作品をネクタイやブックカバーといったプロダクトに落とし込んでいるブランドがあったはず──SNSをさかのぼると、以前は「MUKU」という名前だったブランドは「ヘラルボニー」と改名し、知的障害のある作家たちとより幅広いプロジェクトを展開していた。
「この仕事に関わりたい!」と思った深澤さんは迷わずブランドを手がける株式会社ヘラルボニーにメッセージを送った。すると、武蔵野大学での学びと情熱を評価され、インターンシップとして働くことが決まった。深澤さんの声がはずむ。
「私がすごく引かれたのは、プロダクトの紹介と一緒にその作品を描いた作家さんがどんな人かという紹介があったところです。『障害のある人』という大枠なフィルターで見られてしまう部分を、『さん付け』でその人自身を感じることができるブランドのつくり方をしている点に感銘を受けました。それと同時に、とても心地よくもあり、『これが私の求めているものかもしれない』と胸が高鳴りました」
入社1年目にして、岩手県盛岡市にオープンしたブランド初の常設店の店長を務めた
ヘラルボニーは2018年7月に設立されたばかりのスタートアップ企業で、インターンシップであっても業務の最前線に駆り出された。社長に付き添い商談に立ち会ったり、ポップアップショップで来店者にブランドや作家の話をしたりと、知的障害のある人たちと社会の間にある障壁を取り除くような時間はただただ充実していた。
曰く「マインドの根底にある部分がみんな一緒なので、居心地がよかったです」。「異彩を、放て」をミッションに掲げるヘラルボニーは「異彩を放つ作家とともに、新しい文化をつくるクリエイティブカンパニー」であり、異彩を放つ作家が生み出すアートを社会に届けることで、障害の有無に関係なく、互いの違いを肯定する、誰もが生きやすい世界を築こうとしていた。間違いなく、自分が志した道と重なっていた。
武蔵野大学卒業後の2020年4月から社員としてヘラルボニーで働く。事業の軸は主に二つ。作家のアート作品のデータを用いてバッグやネクタイ、シルクスカーフやハンカチーフといったプロダクトの制作販売をする自社ブランドの運営と、作家のアートデータを活用した企業やブランドとのコラボレーション事業だ。2025年3月15日には東京の銀座にアトリエ併設型ショップとギャラリーを構える「HERALBONY LABORATORY GINZA」、岩手県盛岡市の川徳百貨店(パルクアベニュー・カワトク)に旗艦店として「HERALBONY ISAI PARK」をオープンさせた。
入社6年目を迎えた深澤さんは生き生きとした表情で話す。
「ヘラルボニーはいい意味で障害のイメージを壊し、新しい福祉を創造していく場所です。私はヘラルボニーの一員として、商品企画を通して作家さんの描くアートの質を落とさずにプロダクトとしてこれからも届けていきたいですし、その先で障害のある人たちへのイメージの変容につながることに取り組んでいきたいです。そして今、さまざまな障壁とぶつかっている人たちが少しでも自分らしくあれる社会になればいいなと思っています」
「ヘラルボニーはいい意味で障害のイメージを壊し、新しい福祉を創造していく場所です」
※記事中の肩書きは取材当時のものです。また、学校名は卒業当時の名称です。
関連リンク
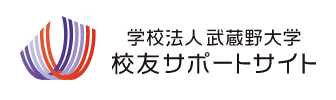


















コメントをもっと見る